学食週間メニュー 12/23~27
今年最後の一週間の学食です。
悔いのないようにいっぱい食べてくださいね~。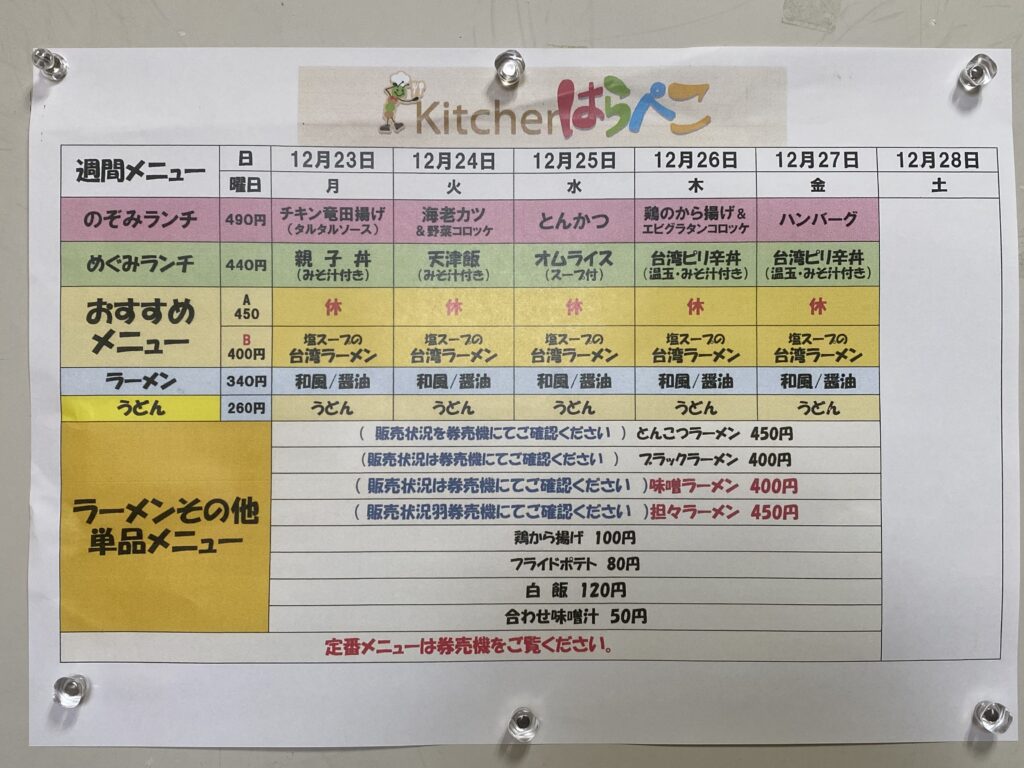

![[イメージ]](https://www.ryujo.ac.jp/blog_office/wp-content/themes/ryujo-office_2020/img/image.jpg)
ブログページ
今年最後の一週間の学食です。
悔いのないようにいっぱい食べてくださいね~。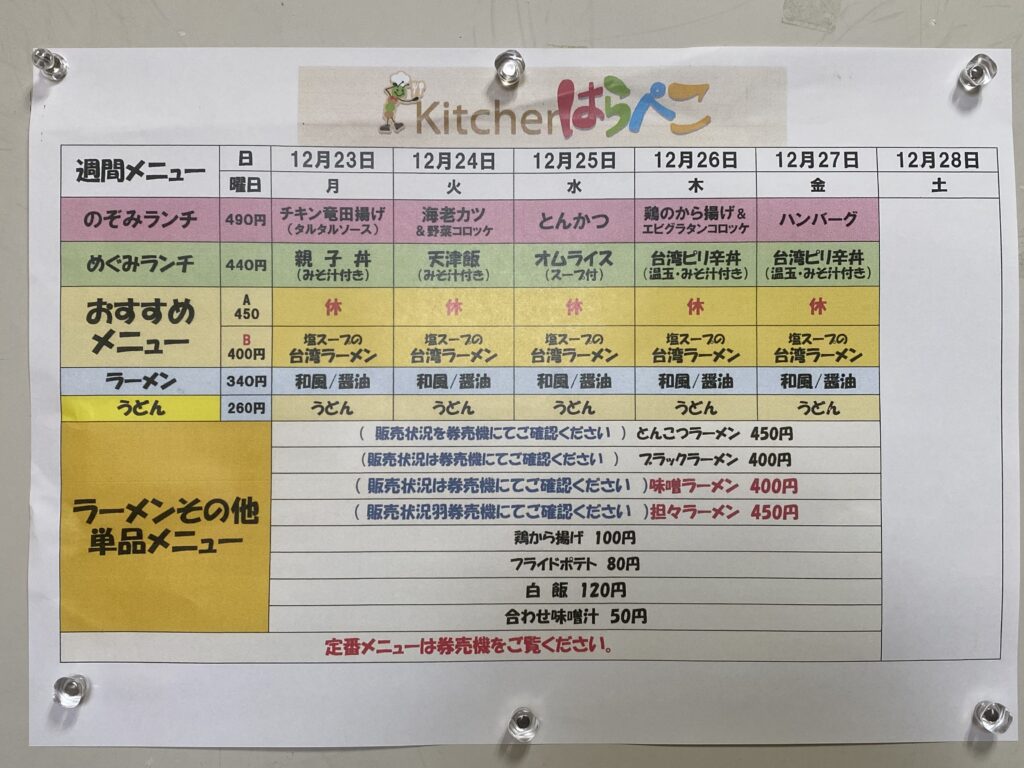
今年の学食は、あと2週間!
今のうちにたくさん食べてくださいね。

もうすぐクリスマス!
楽しいことがいっぱいあるといいですね。

寒い日には温かいものを食べて体も心もほかほかにしましょうね。
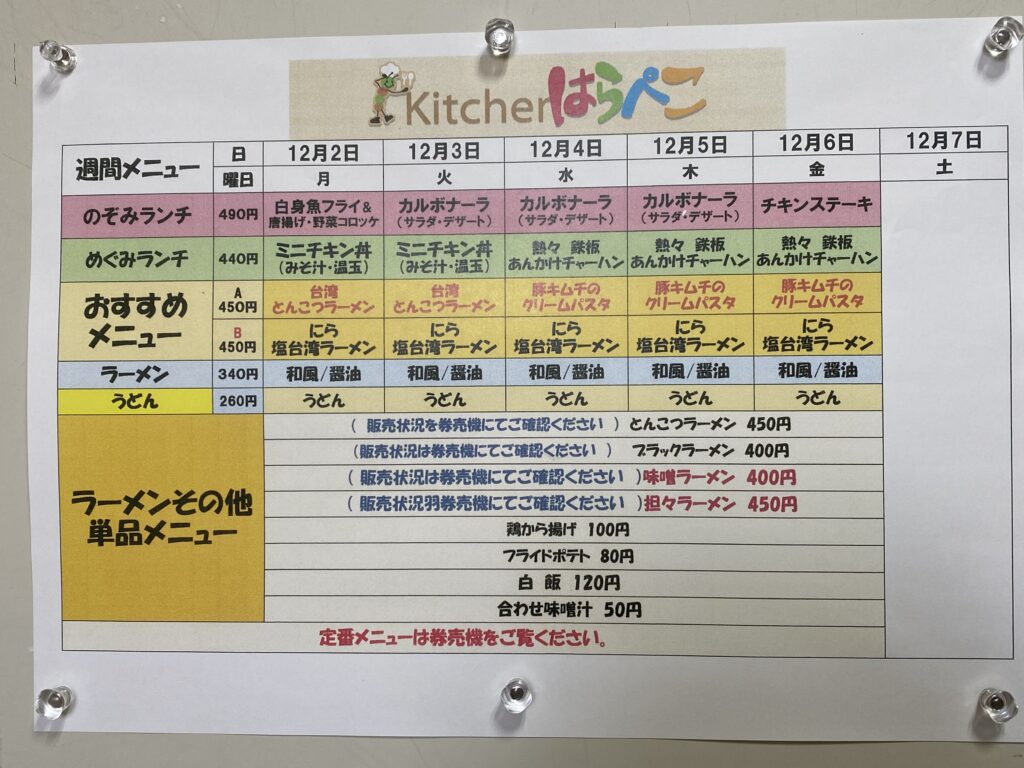
体調を崩している人が多いそうです。いっぱい食べて体力をつけましょう!
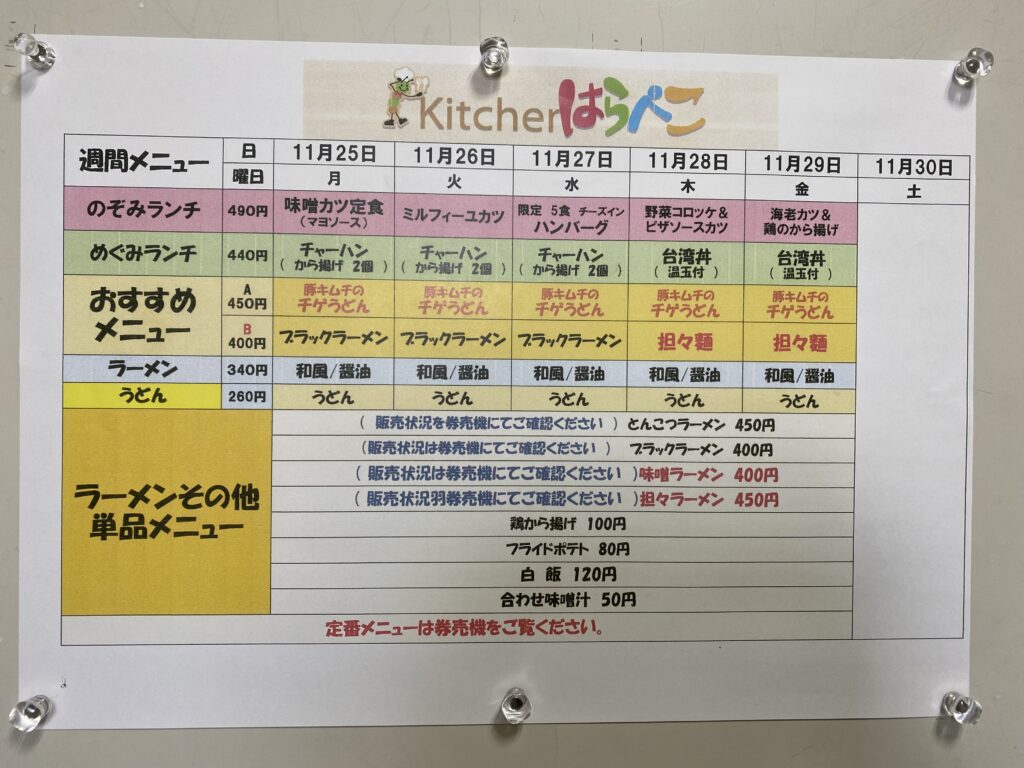
急に寒くなりましたね。体調管理が難しい季節です。
体力と免疫力は落とさないようにしましょう。
実習で人が少ないこの時期は、学食も空いていて、ゆったりできますよ~。
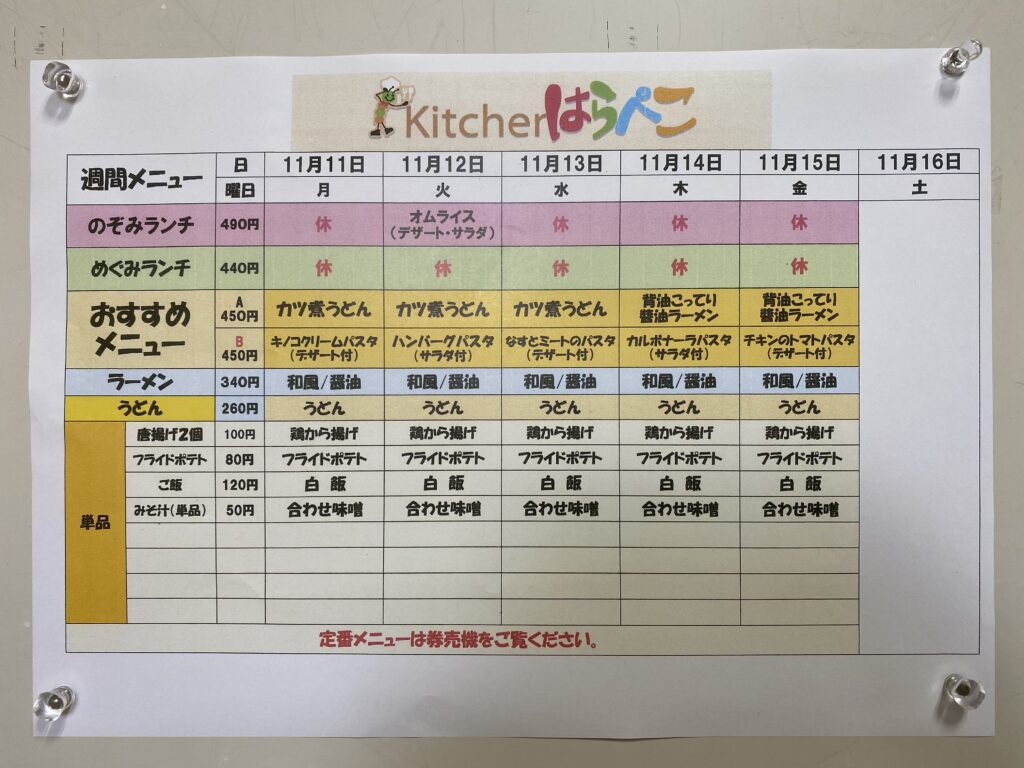
今週は急に寒くなるそうです。温かい食事は嬉しいですね。

食欲の秋!たくさん食べてね。

気温差が激しすぎて体調を崩す季節です。
いっぱい食べて免疫力あげていきましょう⤴

朝晩の寒暖差にも負けないように、ごはんをいっぱい食べましょう!

スポーツの秋・芸術の秋、そして食欲の秋です!
いよいよ、明日から10月。
たくさんの「秋」を楽しみましょう。

そろそろ温かいメニューが食べたくなりますね。

長かった暑い夏もようやく終わりそうです。
ごはんをしっかり食べて、気候の変化に負けないようにしましょう。

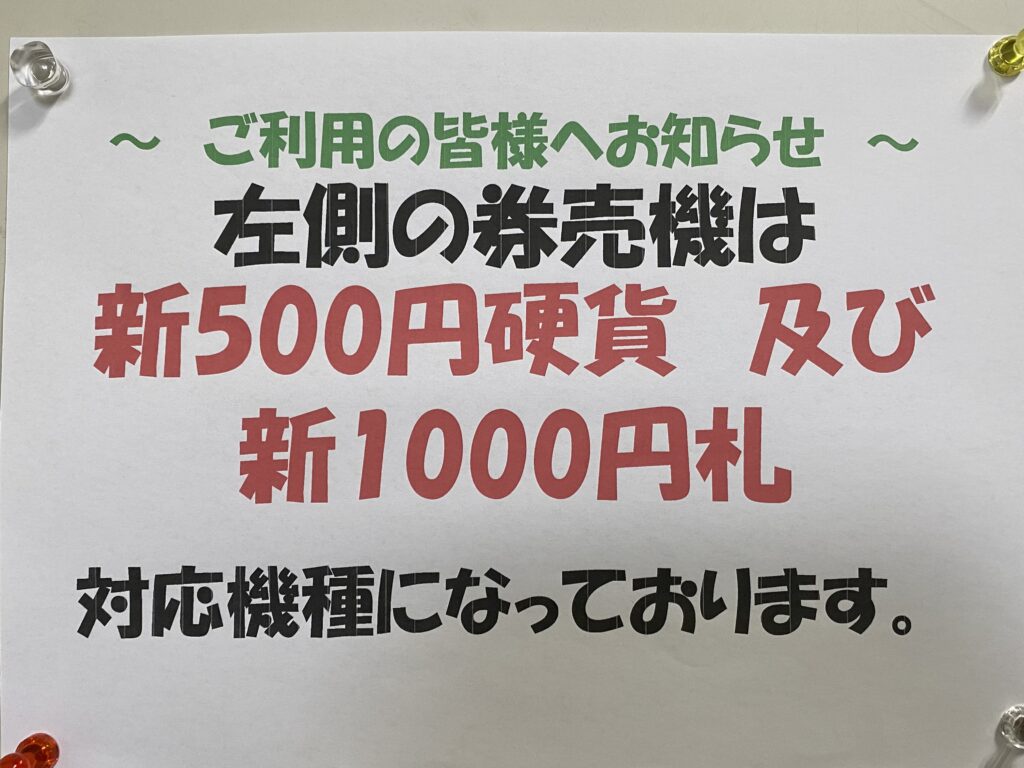
おかえりなさい、有意義な夏休みは過ごせましたか?
学食も始まってますよ。新札も使えますよ~!

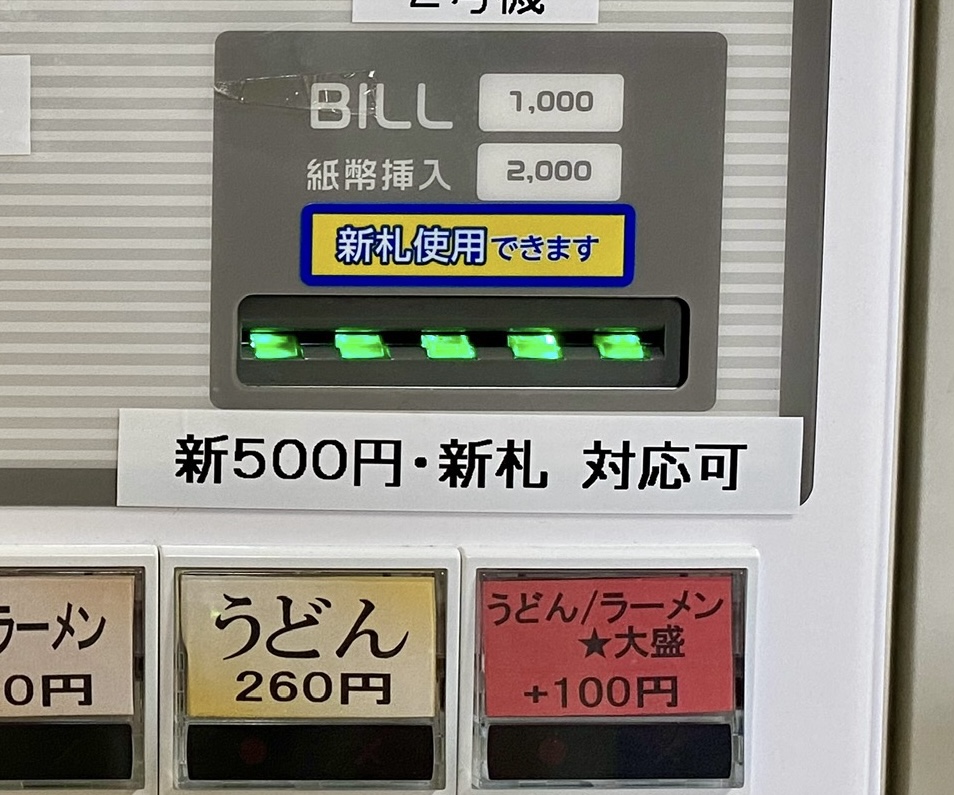
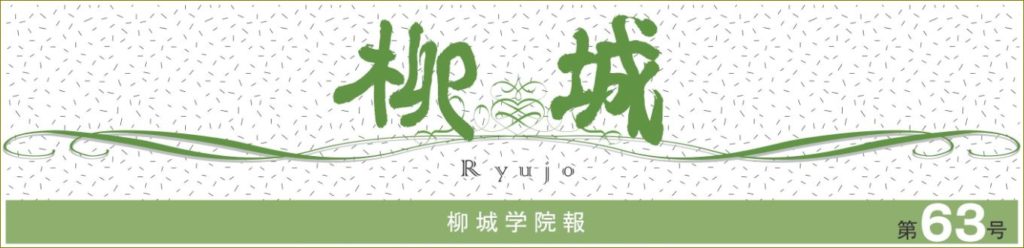 『柳城学院報』120周年記念号が完成したのを受けて、このブログに全ページを掲載することになりました。折を見てバックナンバーを増やしていくつもりです。
『柳城学院報』120周年記念号が完成したのを受けて、このブログに全ページを掲載することになりました。折を見てバックナンバーを増やしていくつもりです。
✝ ✝ ✝
69号(2024/8/1発行)
68号(2023/8/1発行)
67号(2022/8/1発行)
66号(2021/8/1発行)
65号(2020/11/1発行)
64号(2019/8/1発行)
63号(2018/8/1発行)120周年記念号
62号(2017/8/31発行)
61号(2016/8/1発行)
60号(2015/7/1発行)
59号(2014/7/1発行)
58号(2013/7/1発行)
57号(2012/7/1発行)
56号(2011/7/1発行)
55号(2010/7/1発行)
54号(2009/8/15発行)
53号(2008/7/1発行)110周年記念号
【以下『名古屋柳城短期大学報』】
52号(2007/9/20発行)
51号(2006/8/1発行)
50号(2005/7/1発行)
49号(2004/9/1発行)
48号(2003/9/1発行)
47号(2002/6/1発行)
46号(2001/6/1発行)
45号(2000/8/1発行)
43号(1999/7/25発行)
42号(1998/12/20発行)100周年記念号
41号(1998/7/25発行)100周年記念号
39号(1997/7/30発行)
38号(1996/12/20発行)
夏休み前、学食は明日(23日火曜日)までですよ。
みんな、来てね~!

今週は暑くなりそう!
しっかり食べて夏本番に備えましょう。

暑くてバテていませんか?
水分も大事ですが、栄養のあるものも食べましょう。

